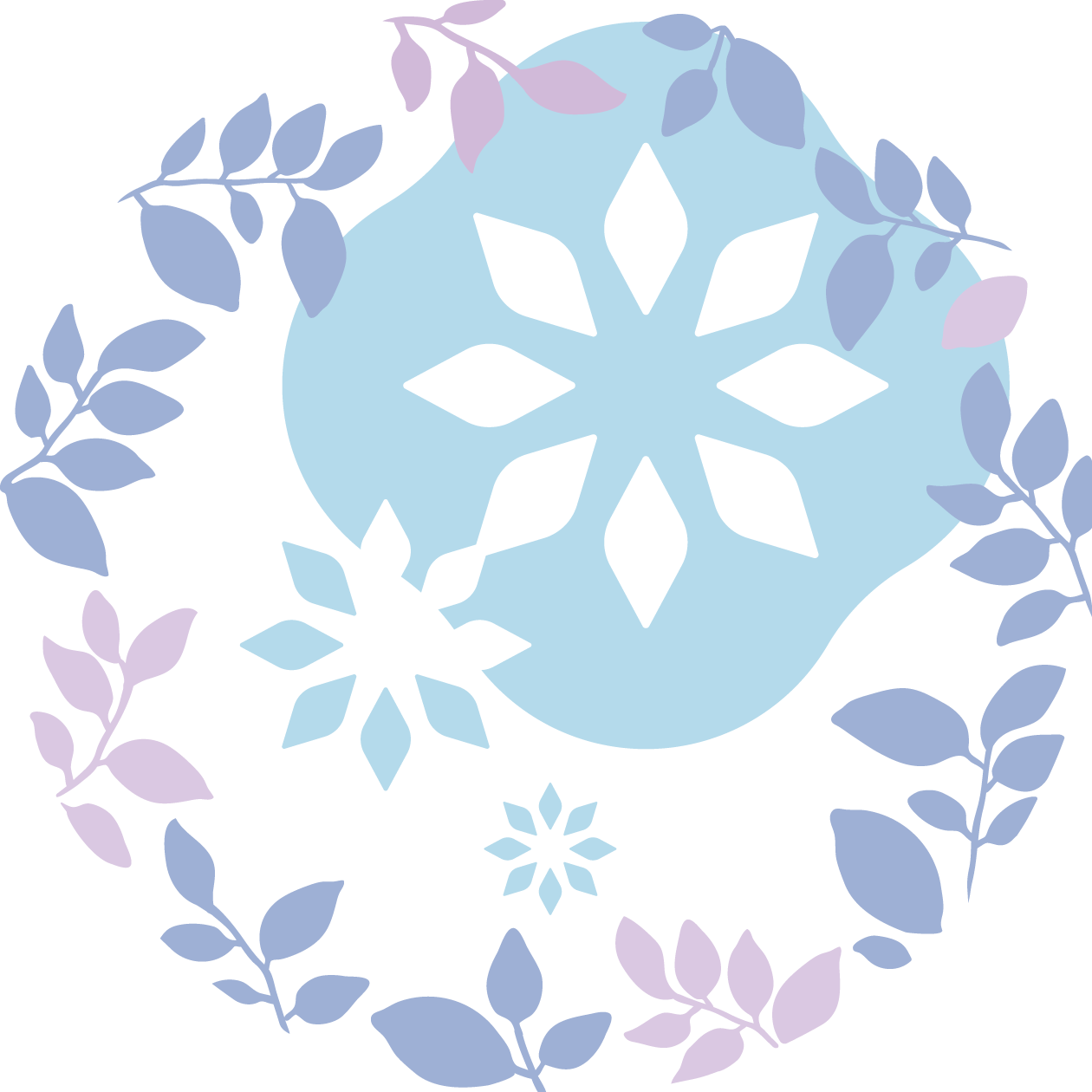登録支援機関になるための要件とは?
投稿日:2025年10月31日

特定技能制度の導入により、外国人材の受け入れが広がる中、「登録支援機関」への関心が高まっています。
外国人が安心して働けるように支援する登録支援機関は、特定技能制度の中でもとても重要な役割を担う存在です。
この記事では、これから登録支援機関として活動したい方に向けて、登録支援機関の要件等について、詳しく解説します。
登録申請の流れについて、お知りになりたい方はこちらの記事をご覧ください。
1.登録支援機関とは
登録支援機関とは、1号特定技能外国人が日本で安心して働き、生活できるようにサポートする機関のことです。受入れ企業から委託を受けて、受入れ企業の代わりに、生活オリエンテーションの実施や住居探しの支援、日本語学習の案内、定期面談等を行います。
支援内容は「出入国管理及び難民認定法(入管法)」で定められており、次の9つの項目にわたります。詳しくはこちらをご覧ください。
- 事前ガイダンスの提供
- 出入国する際の送迎
- 適切な住居の確保に係る支援や生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 日本語学習の機会の提供
- 相談又は苦情への対応
- 日本人との交流促進に係る支援
- 非自発的離職時の転職支援
- 定期的な面談の実施、行政機関への通報
こうした支援を適切に実施するためには、一定の体制や実績が求められるため、登録支援機関として入管庁の登録を受ける必要があります。
登録支援機関は、今では全国に1万件以上が登録されており、外国人を受け入れる企業にとって、特定技能制度の運用を支える心強いパートナーとなっています(登録支援機関登録簿はこちら)。
2.登録支援機関になるための要件
登録支援機関として認められるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 過去5年間、関係法律による刑罰を受けていないこと
- 過去5年間、登録支援機関として登録の取り消しを受けていないこと
- 過去5年間、出入国又は労働関係法令に関し、不正行為を行っていないこと
- 暴力団員等ではないこと
- 行為能力・役員等の適格性があること
- 過去1年間、外国人の行方不明者を発生させていないこと
- 支援責任者及び支援担当者を選任していること
- 中長期在留者の受け入れ実績等があること
- 情報提供・相談等の適切な対応体制があること
- 支援業務実施に係る文書の作成等をすること
- 受入れ企業に対して、中立的な立場の者が支援責任者及び支援担当者であること
- 支援に要する費用を1号特定技能外国人に負担させないこと
- 支援の委託契約締結にあたって、支援に要する費用の額を明示すること
それでは、具体的に見ていきましょう。
(1)過去5年間、関係法律による刑罰を受けていないこと
次のいずれかに該当する者は、登録支援機関になることはできません。なお、申請者が検察官に起訴され、裁判中のため刑が確定していない場合については、刑が確定するまで審査結果は保留になります。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年経過していない者
- 出入国又は労働関係法令に違反し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年経過していない者
- 暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年経過していない者
- 社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年経過していない者
(2)過去5年間、登録支援機関として登録の取り消しを受けていないこと
登録支援機関としての登録の取り消しを受けた場合、その取消日から5年間は登録支援機関になることはできません。これには、取り消された法人の役員も含まれます。
登録取消時の役員には、法人の役員に形式上なっている者だけでなく、実態上法人に強い支配力を持っていると認められる者も対象となります。つまり、業務を執行する社員、取締役、執行役に加えて、これらの人たちと同等以上の支配力を持っていると認められる人が、以前の法人で取り消しを受けてから、5年経たずに新たな登録支援機関を登録申請しても、認められません。
(3)過去5年間、出入国又は労働関係法令に関し、不正行為を行っていないこと
登録申請の日前5年以内に、次のような不正行為を行った者は登録支援機関になることはできません。
- 外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為
- 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為
- 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為
- 上記に掲げるもののほか、外国人の人権を著しく侵害する行為
- 偽変造文書等の行使・提供
- 外国人やその親族等からの保証金の徴収等
- 保証金を徴収している者等から紹介を受けて支援委託契約を締結する行為
- 不法就労者の雇用
- 労働関係法令違反
- 他の機関が不正行為を行った当時に役員等として外国人の受入れ等に係る業務に従事した行為
- 支援委託業務を再委託する行為・再委託を受ける行為
- 1号特定技能外国人支援計画に基づく支援における不正行為
- 1号特定技能外国人支援計画の実施における特異事案報告をしない行為
- 登録支援機関の登録取消しを免れる行為
(4)暴力団員等ではないこと
次に該当する者は、暴力団排除の観点から欠格事由に該当し、登録支援機関になることはできません。
- 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。以下、同じ。)及びその役員が暴力団員等
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(5)行為能力・役員等の適格性があること
次のいずれかに該当する者は、行為能力・役員等の適格性の観点から欠格事由に該当し、登録支援機関になることはできません。
- 精神機能の障害により支援業務の適正な履行に必要な認知等を適切に行うことができない者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 法人の役員、未成年の法定代理人で登録拒否事由(禁固以上の刑に処せられ5年が経過していない者等)に該当する者
(6)過去1年間、外国人の行方不明者を発生させていないこと
過去1年間、登録支援機関になろうとする法人が、外国人について、自らの責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている場合には、当該機関の支援体制が十分であるとは言えないことから、登録支援機関になることはできません。
外国人とは、特定技能外国人だけでなく技能実習生も含まれます。また、責めに帰すべき事由とは、登録支援機関が支援計画を適正に実施していなかった期間や、技能実習制度に係る法令違反・基準に適合しない行為が行われていた期間内に、行方不明者を発生させた場合を指します(1人でも発生させればアウトです)。
(7)支援責任者及び支援担当者を選任していること
登録支援機関になろうとする者は、役員又は職員の中から支援責任者と支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者を選任する必要があります。
支援責任者が支援担当者を兼務することも可能ですが、その場合には、支援担当者として支援業務を行う事務所に所属することが求められます。なお、それぞれの役割は以下のとおりです。
- 支援責任者:支援担当者を監督する人(常勤である必要はありません。)
①支援担当者その他支援業務に従事する職員の管理
②支援の進捗状況の確認
③支援状況の届出
④支援状況に関する帳簿の作成及び保管
➄受入れ企業との連絡調整
➅関係機関との連絡調整
➆その他、支援に必要な一切の事項に関することについての統括管理 - 支援担当者:支援計画に基づく支援を担当する人(常勤であることが求められます。)
◎支援委託契約を締結する受入れ企業ごとに支援担当者1名を選任しなければならないものではなく、支援担当者が複数の1号特定技能外国人の支援を行うことも可能です。
(8)中長期在留者の受け入れ実績等があること
登録支援機関になろうとする者は、次のいずれかに該当する必要があります。
- 過去2年間に、就労資格を持つ外国人の受入れ又は管理を適正に行った実績がある者であること
☝賃金の不払いや雇用契約の不履行等があれば認められません。 - 過去2年間に、報酬を得る目的で業として日本に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験がある者であること
☝相談業務とは、主に在留外国人に対する法律、労働又は社会保険に関する相談業務に従事した経験が想定されており、士業者又は士業法人以外は該当しません。 - 選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上、就労資格を持つ外国人の生活相談業務に従事した一定の経験を持つ者であること
☝生活相談業務とは、生活に必要な契約に係る支援、生活オリエンテーション、定期面談等、業務として行われたものを指します。職業紹介事業者が、求人情報を紹介する行為は対象外です。 - 1~3のいずれかに該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として入管庁長官が認める者であること
☝支援業務を適正に実施できるかどうかは、提出資料に基づき、個別に判断されます。
(9)情報提供・相談等の適切な対応体制があること
支援業務の適正性の確保の観点から、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な情報提供体制があること
- 担当職員を確保して、特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な相談体制があること
- 支援責任者又は支援担当者が特定技能外国人及びその監督をする立場にある者との定期的な面談体制があること
(10)支援業務実施に係る文書の作成等をすること
登録支援機関に対して、支援計画の実施状況に関する文書を作成し、支援の対象である1号特定技能外国人について、雇用契約終了日から1年以上、その文書を備え置いておくことを求めるものです。備えておく文書の種類は次のとおりです。なお、紙の代わりにデータで保存することも認められています。
- 支援実施体制に関する管理簿
- 支援の委託契約に関する管理簿
- 支援対象者に関する管理簿
- 支援の実施に関する管理簿
(11)受入れ企業に対して、中立的な立場の者が支援責任者及び支援担当者であること
支援の適正性や中立性の確保の観点から、支援責任者又は支援担当者が次のいずれかの場合に該当する場合は、登録支援機関になることはできません。
- 受入れ企業の役員の配偶者や2親等内の親族であること
- 受入れ企業の役員と社会生活上密接な関係を持つ者であること
- 過去5年間に受入れ企業の役員又は職員であったにもかかわらず、その企業から委託を受けた支援業務に係る支援責任者になろうとする者であること
(12)支援に要する費用を1号特定技能外国人に負担させないこと
1号特定技能外国人の支援(義務的支援)に要する費用は、1号特定技能外国人に直接的又は間接的にも負担させないことが求められます。このことについては、事前ガイダンスだけでなく、生活オリエンテーションにおいても当該外国人に説明する必要があります。
(13)支援の委託契約締結にあたって、支援に要する費用の額を明示すること
支援の適正性の確保の観点から、登録支援機関は受入れ企業から支援計画の全部の実施の委託を受ける際は、支援業務に要する費用の額とその内訳を示すことを求めるものです。
支援委託費用については、法令上の上限はありませんが、支援委託契約を締結する際に、当該費用の額とその内訳を「支援委託手数料に係る説明書(予定費用)」で示す必要があります。
3.登録支援機関がやってはいけないこと
ここまで登録支援機関になるための要件を見てきましたが、登録後に受入れ企業とのやりとりの中で、誤って行ってしまうことの多い「禁止行為」についても確認しておきましょう。
(1)支援計画の作成は受入れ企業の仕事
登録支援機関は、特定技能外国人の生活支援や日本語学習支援等を行う専門機関ですが、報酬を得て支援計画そのものを作成することはできません。
支援計画は、雇用主である受入れ企業が作成するものです。(ただし行政書士であれば、企業から依頼を受けて代わりに作成することも可能です。)
登録支援機関は、作成の補助(アドバイスやチェック等)まではOKですが、実際の作成はできませんので、ご注意ください。
(2)ビザ申請書類の作成もNG
在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更申請等について、報酬を得て入管に提出する書類を作成できるのは、行政書士又は弁護士だけです。
登録支援機関は、たとえ申請取次資格を持っていても、書類作成はできません。登録支援機関ができることは、あくまでも、本人に代わって提出するのみです。
もし、以下のような形で報酬を得て、申請書等を作成した場合は行政書士法違反となり、刑罰の対象になります。2026年1月1日改正施行の行政書士法で、より明確に定められていますので、ご注意ください。
-
「コンサルティング料」「サポート料」等の名目で書類作成料を得る
-
月額支援料に書類作成料を含めた「パッケージ料金」を得る
-
「無料」と称しながら他のサービス料金に上乗せする
-
年会費や登録料等の名目で書類作成料を得る
-
登録支援機関が行政書士を雇用・委託して申請業務を行う
4.まとめ
この記事では、登録支援機関になるための要件を中心に解説しました。
登録支援機関は、特定技能外国人が日本で安心して働くための重要な存在です。登録には一定のハードルがありますが、正しく準備を進めれば、社会貢献性の高い事業として大きな可能性があります。
当事務所では、登録支援機関の新規登録申請のご相談を承っております。初めての方でも安心して進められるよう、必要書類の作成から登録完了までしっかりサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。
お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
新着情報・お知らせ
かざはな行政書士事務所

住所
〒739-0041 広島県東広島市西条町寺家
受付時間
10:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日(予約対応可)
対応地域
広島県を中心に、岡山県、山口県、島根県、鳥取県および全国オンライン対応可能