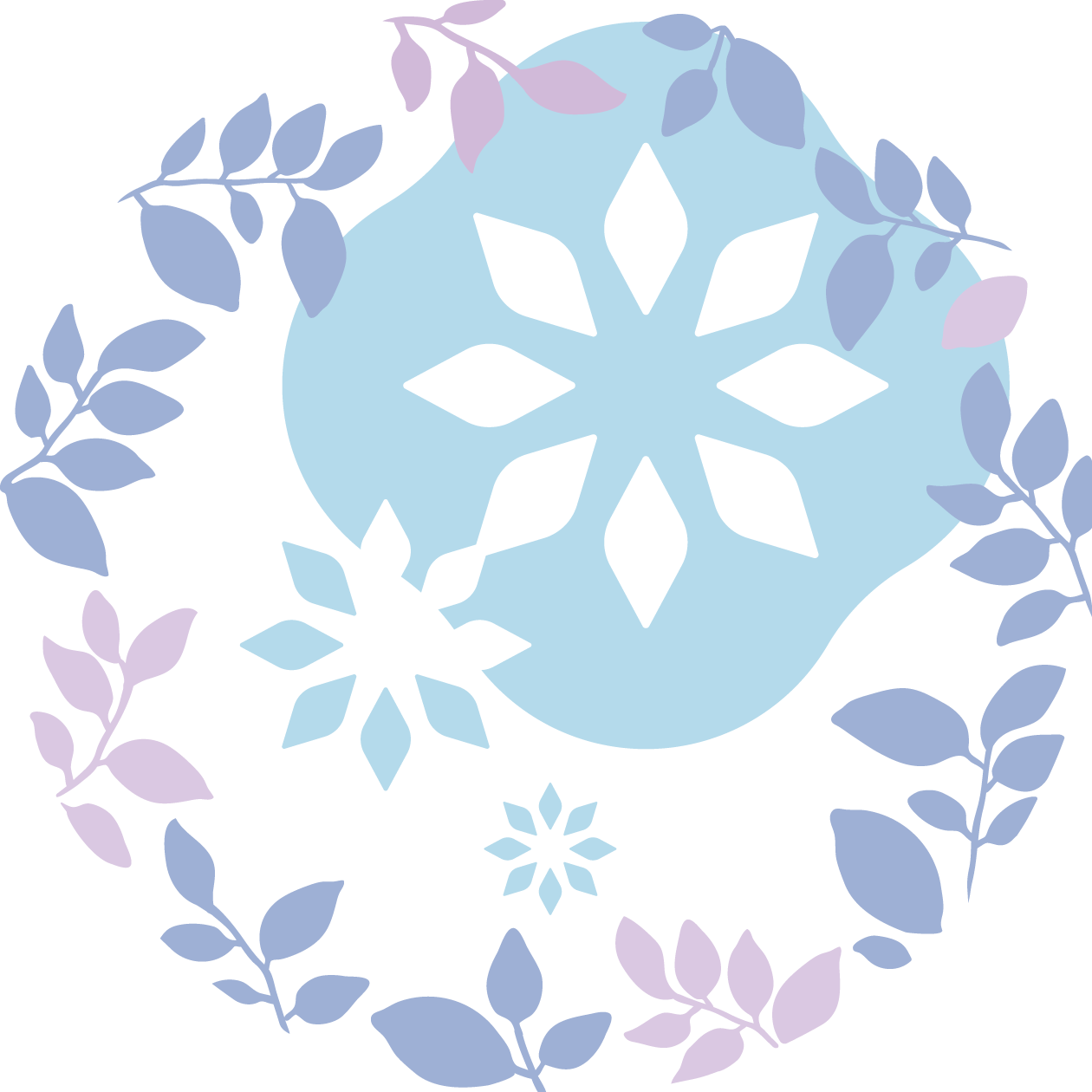特定技能外国人を受け入れるための受入機関適合性とは?
投稿日:2025年9月28日

特定技能外国人を雇用するには、企業が「受入機関」として、出入国在留管理庁(以下、入管)の定める条件を満たす必要があります。その条件は5つありますが(詳しくはこちら)、そのうちの1つに「受入機関適合性を満たす」という条件があります。
この受入機関適合性を満たしていなければ、特定技能の在留資格が許可されず、特定技能外国人を就労させることはできません。
この記事では、受入機関適合性の要件を詳しく解説します。
1.受入機関適合性の要件
受入機関適合性には以下の要件があります(参考:特定技能外国人受入れに関する運用要領)。
この中で1つでも満たさないものがあれば(欠格事由に該当すれば)、その日から5年間、特定技能外国人を受け入れることができないため、非常に気を付けて確認する必要があります。
- 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守すること
- 非自発的離職者を発生させないこと(特定技能雇用契約締結の前1年及び締結後)
- 行方不明者を発生させないこと(特定技能雇用契約締結の前1年及び締結後)
- 関係法律による刑罰を受けていないこと(刑に処せられ、その執行後又は執行を受けることが無くなった日から5年を経過していること)
- 実習認定の取消しを受けた場合は、取消しを受けてから5年が経過していること
- 出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行っていないこと(特定技能雇用契約締結の前5年及び締結後)
- 暴力団員等ではないこと
- 行為能力・役員等の適格性があること
- 特定技能外国人の活動状況に係る文書を作成し、雇用契約終了の日から1年以上保管すること
- 特定技能外国人とその親族が、保証金の徴収・違約金契約等を締結させられていないこと
- 特定技能外国人に対する義務的支援の費用を外国人に負担させないこと
- 特定技能外国人を派遣労働者として受け入れる場合、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者等で、適当と認められる者であるほか、派遣先も1~4の基準に適合すること
- 会社が労災保険の適用事業所である場合、労災保険に係る保険関係の届出を適切に行うこと
- 会社が事業を安定的に継続することができる財政的基盤を持っていること
- 報酬の支払い方法が口座振込であること
- 地域における共生社会の実現のために寄与する責務を果たしていること
- 特定産業分野ごとの特有の事情に応じて個別に定める基準に適合していること
それでは、それぞれ細かく見ていきましょう。
(1)労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守すること
受入機関が労働関係法令、社会保険関係法令及び租税関係法令を遵守していることを求めるものです。
- 労働関係法令の遵守
①労働基準法等の基準に基づいて雇用契約が締結されていること
②雇用保険及び労災保険の適用事業所である場合は、当該保険の適用手続き及び保険料の納付を適切に行っていること
③特定技能外国人との雇用契約にあたり、あっせんする者がいる場合は、適切な許可を受けている事業者から求人のあっせんを受けていること
※②について、労働保険料の未納があっても、入管の助言・指導に基づき納付手続きを行った場合は、遵守していると評価されます。また、労災保険の適用事業所でない場合は、労災保険に代わる民間保険に加入させることが求められます。①~③はあくまでも労働関係法令の例示にすぎないため、その他の労働関係法令(例:最低賃金法、労働安全衛生法等)の1つでも遵守していないものがあれば、受入適合性を満たしていない(欠格事由に該当する)と判断されます。 - 社会保険関係法令の遵守
①健康保険及び厚生年金保険の適用事業所で、所定の保険料を適切に納付していること
②健康保険及び厚生年金保険の適用事業所ではない場合は、受入機関(事業主本人)が国民健康保険及び国民年金に加入し、所定の保険料を適切に納付していること - 租税関係法令の遵守
①法人の場合、国税(源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税)及び地方税(法人住民税)を適切に納付していること
②個人事業主の場合、国税(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)及び地方税(個人住民税)を適切に納付していること
※納付すべき税に未納があっても、入管の助言・指導に基づき納付した場合は、遵守していると評価されます。一方、特定技能外国人から特別徴収した個人住民税を受入機関が納入していないことによって未納があることが判明した場合は、遵守していないと評価され、欠格事由に該当しますので、注意が必要です。
(2)非自発的離職者を発生させないこと
受入機関が、現に雇用している国内労働者を非自発的に離職させ、その補填として特定技能外国人を受け入れることは、人手不足に対応するための人材の確保という特定技能制度の趣旨に沿わないことから、特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないことを求めるものです。対象期間は、特定技能外国人との雇用契約を締結する前の1年以内及び締結後も含まれます。
非自発的離職に該当しない場合は次のとおりです。
- 定年その他これに準ずる理由により退職した場合
- 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合
- 有期労働契約の期間満了時に労働契約を更新しないことにより終了された場合
- 自発的に離職した場合
一方、非自発的離職に該当する場合は次のとおりです。
- 人員整理を行うための希望退職の募集又は退職勧奨を行った場合
- 労働条件に係る重大な問題(賃金低下、過度な時間外労働等)があったと労働者が判断した場合
- 就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、嫌がらせ等)があった場合
- 労働者の責めに帰すべき理由によらない有期労働契約の終了
- 試用期間後に本採用拒否をしている場合
(3)行方不明者を発生させないこと
受入機関が雇用する外国人について、責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている場合には、当該機関の受け入れ体制が十分であるとは言えないことから、雇用契約を締結する前の1年以内及び締結後に行方不明者を発生させていないことを求めるものです。
外国人とは、特定技能外国人だけでなく技能実習生も含まれます。また、責めに帰すべき事由とは、受入機関が雇用条件どおりに賃金を払っていない場合や支援計画を適正に実施していない場合等を指し、法令違反や基準に適合しない行為が行われていた期間内に外国人が行方不明となった場合が欠格事由の対象となります(1人でも発生させればアウトです)。
(4)関係法令による刑罰を受けていないこと
次のいずれかに該当する場合は、欠格事由に該当します。また、いずれも刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者がその対象となります。
- 拘禁刑以上の刑に処せられた者
- 出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者
- 暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者
- 社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者
なお、受入機関となる予定の企業の事業主等が検察庁から起訴され、裁判中のため刑が確定していない場合は、在留資格認定証明書交付申請(海外在住の外国人を呼び寄せるための申請)については、刑が確定するまで審査結果は保留となります。
(5)実習認定の取消しを受けた場合は、取消しを受けてから5年が経過していること
実習実施者として技能実習生を受け入れていた際に、実習認定の取消しを受けた場合、当該取消日から5年を経過しない者(取り消された者の法人の役員であった者を含む)は、受入機関になることはできません。
なお、欠格事由の対象となる役員は、法人の役員に形式上なっている者のみならず、実態上法人に対して強い支配力を持つと認められる者についても対象となります。
(6)出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行っていないこと
雇用契約の締結の日前の5年以内又はその締結の日以後に、出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を行った者は、欠格事由に該当し、受入機関になることはできません。不正又は不当な行為については、個別具体的な事案の重大性に応じて該当性が判断されることとなります。なお、不正行為として主に認定される行為は次のとおりです。
- 外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為
- 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為
- 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為
- 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為
- 1から4に掲げるもののほか、外国人の人権を著しく侵害する行為
- 偽変造文書等の行使・提供
- 外国人やその親族等からの保証金の徴収等
- 届出の不履行又は虚偽の届出
- 報告徴収に対する妨害等
- 改善命令違反
- 不法就労者の雇用
- 労働関係法令違反
- 技能実習制度における不正行為
- 他の機関が不正行為を行った当時に役員等として外国人の受入れ等に係る業務に従事した行為
- 1号特定技能外国人支援計画に基づく支援における不正行為
欠格事由該当期間の起算点は、不正行為が終了した日となります。例えば、暴行等の不正行為が発覚した場合、暴行行為の最終日が不正行為が終了した日となり、そこから欠格事由該当期間が始まります。
(7)暴力団員等ではないこと
次に該当する者は、暴力団排除の観点から欠格事由に該当し、受入機関になることはできません。
- 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。以下、同じ。)及びその役員が暴力団員等
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(8)行為能力・役員等の適格性があること
次のいずれかに該当する者は、行為能力・役員等の適格性の観点から欠格事由に該当し、受入機関になることはできません。
- 精神機能の障害により雇用契約の適正な履行に必要な認知等を適切に行うことができない者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 法人の役員、未成年の法定代理人で特定技能基準省令第2条第1項第4号各号(ワを除く)に該当する者
(9)特定技能外国人の活動状況に係る文書を作成し、雇用契約終了の日から1年以上保管すること
受入機関に対し、特定技能外国人の活動状況に関する文書を作成し、特定技能外国人が業務に従事する事業所に備えて置くことを求めるものです。備えて置かなければならない活動の内容に関する文書は、次のとおりです。
- 特定技能外国人の名簿(氏名、国籍・地域、生年月日、性別、在留資格、在留期間、在留期間満了日、在留カード番号、外国人雇用状況届出の届出日)
- 特定技能外国人の活動状況に関する帳簿(活動場所、従事した業務内容、雇用状況、労働保険適用状況、社会保険加入状況、安全衛生確保状況、外国人の受入れに要した費用の額及び内訳、外国人の支援に要した費用の額及び内訳、休暇の取得状況、行政機関からの指導又は処分に関する内容)
- 特定技能雇用契約の内容
- 雇用条件
- 特定技能外国人の待遇に係る事項が記載された書類(賃金台帳等)
- 特定技能外国人の出勤状況に関する書類(出勤簿等の書類)
上記文書は、書面だけでなくデータで作成・保存することも可能です。
(10)特定技能外国人とその親族が、保証金の徴収・違約金契約等を締結させられていないこと
受入機関は、特定技能外国人及びその親族等が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を締結させられている等の場合には、そのことを認識して雇用契約を締結していないことを求めるものです。違約金等を定める不当な契約例は次の通りです。
- 失踪する等の労働契約の不履行に係る違約金を定める契約
- 入管や労働基準監督署に法令違反に関する相談をすること、休日に許可を得ずに外出すること、作業時間中にトイレ等で離席すること等を禁じてその違約金を定める契約
- 外国人が一定期間勤務することを停止条件として貸付金の返済を免除する契約
- 外国人が返済途中に退職した場合に貸付金の残額を一括で返済する内容の契約
- 商品又はサービスの対価として不当に高額な料金の徴収を予定する契約
規制の対象は、受入機関、登録支援機関、職業紹介事業者等、雇用契約に基づく特定技能外国人の日本の活動に関与する仲介事業者のみならず、海外のブローカー等も含み、幅広く規制の対象とするとされています。
また、特定技能外国人及びその親族が、上記のような不当な契約を締結させられていること等を認識した状態で雇用契約を締結し、特定技能外国人を受け入れた場合、6の出入国又は労働関係法令に関する不正行為に該当するとして、欠格事由に該当し、そこから5年間特定技能外国人を受け入れることができなくなります。よって、雇用契約を締結する時に十分に確認してください。加えて、1号特定技能外国人を雇用する受入機関は、事前ガイダンスでも保証金・違約金契約は違法であり、禁止されていることについて説明するとともに、保証金の徴収等が無いことを確認してください。
(11)特定技能外国人に対する義務的支援の費用を外国人に負担させないこと
1号特定技能外国人に対する支援にかかる費用は、受入機関が負担すべき費用であることから、1号特定技能外国人に直接的又は間接的にも負担させないことを求めるものです。
1号特定技能外国人の受入れにあたっては、事前ガイダンス及び生活オリエンテーションにおいて、支援にかかる費用を直接的にも間接的にも負担させないことについて、説明する必要があります。
(12)労働者派遣の場合、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者等で、適当と認められる者であるほか、派遣先も1~4の基準に適合すること
特定技能外国人を派遣労働者として受け入れ可能な産業分野は、2025年9月時点で農業と漁業のみですが、この産業分野において、派遣元は受入機関適合性を満たすとともに、当該外国人が従事する予定の特定産業分野に関する業務を行っていることが求められます。また、派遣先も1~4の基準を満たしていることが求められます。
(13)会社が労災保険の適用事業所である場合、労災保険に係る保険関係の届出を適切に行うこと
特定技能外国人への労働者災害補償保険の適用を確保するため、受入機関が労災保険の適用事業所である場合、労災保険に係る保険関係の成立の届出を適切に履行していることが求められます。
(14)会社が事業を安定的に継続することができる財政的基盤を持っていること
特定技能外国人の安定した就労活動を確保するために、受入機関に雇用契約を継続して履行する体制を持っていることを求めるものです。つまり、受入機関が雇用契約を確実に履行できる財政的基盤を持っていることを求められているということです。財政的基盤の有無については、直近年度末における欠損金の有無や債務超過の有無等から総合的に判断されることになります。
(15)報酬の支払方法が口座振込であること
特定技能外国人に対する報酬の支払をより確実かつ適正なものとするため、当該外国人に対して、報酬の支払方法として口座振込があることを説明した上で、当該外国人の同意を得た場合に、報酬の口座振込を行うことを求めるものです。
なお、口座振込以外の方法を採った場合は、受入機関が1年に1度提出する「受入れ・活動・支援実施状況に関する届出」の際に、報酬支払証明書を提出し、入管の確認を受けることが求められます。
(16)地域における共生社会の実現のために寄与する責務を果たしていること
特定技能外国人に関し、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を求められたときは、求めに応じ必要な協力をすることを求めるものです。
地方公共団体が実施する共生施策とは、例えば各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策等が想定されます。
受入機関は、①初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、当該外国人と雇用契約締結後、在留資格諸申請の前に、また②既に特定技能外国人を受け入れている場合は、当該外国人の在留資格諸申請の前に、市区町村に対して、協力確認書を提出する必要があります。
協力確認書は、当該外国人が活動する事業所の所在地と当該外国人が住む住居地の市区町村にそれぞれ提出する必要がありますが、所在地と住居地が同一の市区町村の場合は、1通の提出で大丈夫です(郵送受付のみかオンライン提出も可能かは市区町村によって異なりますので、必ずHPで確認してください)。また、その提出後に他の特定技能外国人を雇用する場合は、再提出不要です。ただし、協力確認書に記載した事項に変更が生じた場合は、改めて提出する必要があります。なお、特定技能外国人の転職・転出や帰国の際には、受入機関から市区町村に連絡する必要はありません。
(17)特定産業分野ごとの特有の事情に応じて個別に定める基準に適合していること
特定産業分野ごとの特有の事情に応じて、個別に定める基準に適合していることを求めるものです。例えば、建設分野と介護分野においては、特定技能外国人の受け入れ人数枠が設けられています。それぞれの産業分野の運用要領別冊(分野別)で確認する必要があります。
2.まとめ
この記事では、特定技能外国人を受け入れる際に企業が満たすべき「受入機関適合性」の要件について解説しました。
ご紹介したとおり、要件は多岐にわたりますが、特定技能の雇用にはこの適合性を満たすことが不可欠です。法令遵守や支援体制の整備等、多くの準備が必要ですが、適切に対応すれば外国人材を安定的に受け入れることができます。
「自社が基準を満たしているか不安」「書類整備に手が回らない」といった場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。安心して特定技能外国人を受け入れられる体制づくりを丁寧にサポートいたします。

この記事の監修者
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。
お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
新着情報・お知らせ
かざはな行政書士事務所

住所
〒739-0041 広島県東広島市西条町寺家
受付時間
10:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日(予約対応可)
対応地域
広島県を中心に、岡山県、山口県、島根県、鳥取県および全国オンライン対応可能