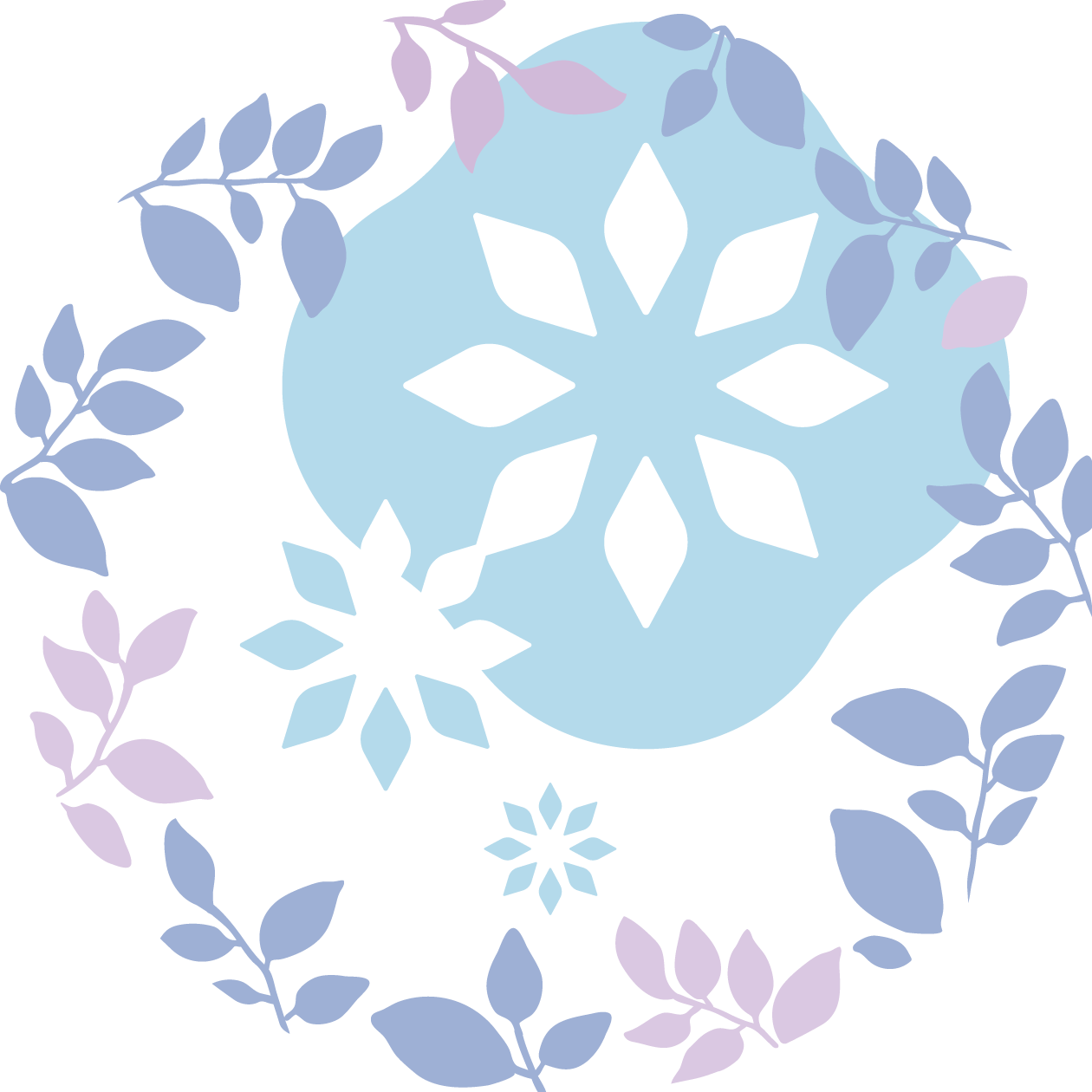特定技能の支援計画とは?外国人雇用に必須の準備を解説
投稿日:2025年9月19日

特定技能1号の在留資格を持つ外国人を雇用する際、受入れ企業には1号特定技能外国人の支援計画の作成と実施が義務付けられています。
支援計画は、特定技能外国人が安心して日本で働き、生活できるようにするためのものです。特定技能外国人の支援計画を作成しなければ、特定技能1号の在留資格の許可が下りないため、必ず準備する必要があります。
この記事では、特定技能の支援計画の内容について詳しく解説します。
1.特定技能の支援計画とは
支援計画とは、1号特定技能外国人を受け入れる企業が入管に提出しなければならない計画書です。入管法に基づき、外国人が日本で安心して就労・生活できるようにすることを目的としています。受入れ企業が1号特定技能外国人を同時に複数に雇用する場合は、まとめて作成することができます。
また、支援計画を作成するのは受入れ企業ですが、必要に応じて、登録支援機関に作成の補助をしてもらうことも可能とされています。ただし、あくまでも作成の補助ですので、行政書士又は弁護士でない登録支援機関が、業として支援計画を作成することは行政書士法違反となりますので、注意してください。
一方、支援計画の実施を登録支援機関に委託することは可能です。多くの受入れ企業が登録支援機関に支援計画実施の全部委託をしています。委託する場合は、月額支援委託料がかかります。1人当たり2~3万円程度で、登録支援機関によって金額は異なります。なお、この支援計画の実施(義務的支援)に係る費用を外国人本人に負担させてはいけません。すべて受入れ企業が負担することとなります。
2.特定技能の支援計画の内容(義務的支援)
特定技能の支援計画の内容は特定技能基準省令で定められており、次の9つの内容を必ず盛り込む必要があります。なお、入管に提出する支援計画書の様式は日本語のほか、英語、タガログ語、ベトナム語等10言語用意されており、当該外国人が理解できる言語で作成し、外国人がその内容を理解したうえで、署名する必要があります(様式はこちらのページからダウンロードできます)。
(1)事前ガイダンスの提供
受入れ企業又は支援の全部委託を受けた登録支援機関は、特定技能雇用契約締結後、特定技能1号ビザの申請をするまでに、当該外国人に対して、その外国人が理解できる言語で次の内容の情報の提供を実施しなければなりません(義務的支援)。また、実施時間が1時間に満たないような場合は、事前ガイダンスを適切に行ったとは評価されない可能性があります。なお、実施方法は対面でもZOOM等のオンラインでも可能です。
- 従事する業務の内容、報酬額やその他の労働条件(安全又は衛生等)に関する事項
- 日本において行うことができる活動の内容
- 入国手続きに関する事項 ※新たな入国の場合と既に日本に在留している場合とで手続きの流れが異なりますので、それぞれの場合に応じて説明します。
- 保証金の徴収、契約の不履行についての違約金契約等の締結の禁止 ※本人だけでなくその家族に対しても禁止されていることを説明します。
- 入国準備に関し、外国の機関に支払った費用について、その費用の額及び内訳を十分に理解して支払わなければならないこと
- 支援に要する費用を負担させないことととしていること
- 入国する際の送迎に関する支援の内容 ※既に日本に在留している外国人の場合は不要です。
- 住居の確保に関する支援の内容 ※部屋の広さや外国人が負担する家賃等の情報を提供します。
- 相談・苦情の対応に関する内容 ※対応可能時間や対応方法等の情報を提供します。
- 受入れ企業又は登録支援機関の支援担当者の氏名及び連絡先(メールアドレス等)
ちなみにこの項目の任意的支援としては、①入国時の日本の気候、服装、②本国から持参すべき物、持参した方がよい物、持参してはならない物、③入国後、当面必要となる金額及びその用途、④受入れ企業から支給される物(作業着等)等に関する情報の提供があります。事前ガイダンス実施後、就労開始前でも当該外国人からの質問や相談に適切に応じることが望まれます。
(2)出入国する際の送迎
1号特定技能外国人が入国する際は、日本に上陸する手続きをする空港等から受入れ企業の事業所又は当該外国人の住居まで送迎することが求められます。入国する際の送迎が過度な負担にならないよう、事前ガイダンスの際に、受入れ企業の事業所又は住居の最寄りの空港を案内する等、出迎えに適した入国経路を決めておくとよいでしょう。ちなみに、既に日本に在留している外国人については、支援対象外です。
また、出国する際は、当該外国人が出国の手続きをする空港等まで送迎を行うことが求められます。さらに、出国の際は単に送迎するだけでなく、保安検査場の前まで同行し、入場することを確認する必要があります。既に特定技能外国人が就業中に住んでいた住居を退去している場合は、当該外国人の滞在先を把握し、確実に連絡を取る手段を確保しておかなければなりません。
送迎方法としては、車両以外にも鉄道やバス等の公共交通機関の利用も可能です。登録支援機関に委託している場合は、登録支援機関が送迎を行うこととなりますが、注意すべき点があります。登録支援機関が車両で送迎する場合、道路運送法上の必要な許可を受けている必要がありますので、その許可を受けていなければ、公共交通機関を利用するようにしましょう。なお、一時帰国の際の出入国は、この支援対象に含まれません。
この項目の任意的支援としては、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する等、既に日本に在留している外国人を特定技能外国人として雇用する場合の日本国内の移動について、送迎を実施することや移動費用を受入れ企業が負担すること等が挙げられます。送迎を実施しない場合でも、事業所までスムーズに移動できるよう、当該外国人に交通手段や緊急時の連絡先を伝えておくことが望まれます。
(3)適切な住居の確保に係る支援や生活に必要な契約支援
1号特定技能外国人が住居を確保していない場合、次のいずれかの方法(外国人が希望する方法)で支援を行うことが求められます。また、この支援は、当該外国人が転居する場合も求められます。さらに、この住居の確保に係る支援は、当該外国人の離職が決まった後も、雇用契約が有効である間は行うことが求められますので注意してください。
- 不動産仲介事業者や賃貸物件の情報を提供し、必要に応じて住宅確保に係る手続きに同行し、住居探しの補助を行う。また、賃貸借契約の締結時に連帯保証人が必要な場合に、適当な連帯保証人がいないときは、支援対象者の連帯保証人となる又は利用可能な家賃債務保証業者を確保し、自らが緊急連絡先となる。
- 自ら賃貸借人となって賃貸借契約を締結した上で、1号特定技能外国人の合意の下、住居として提供する。
- 所有する社宅等を1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。
1の場合、敷金・礼金等は、基本的には1号特定技能外国人本人が負担するものですが、受入れ企業が任意に全額負担してもよいとされています。また、家賃債務保証業者を利用した場合は、保証料は受入れ企業が負担する必要があります。
2又は3の場合で、受入れ企業が賃借人となる場合は、1号特定技能外国人に社宅等を貸与することで経済的な利益を得てはいけません。借り上げ物件であれば、借り上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない)を入居する外国人の人数で割った額以内の額でなければなりません。自己所有物件であれば、実際に建設・改築等に要した費用、物件の耐用年数、入居する外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額でなければなりません。また、社宅等を提供する場合には、他の入居者の家賃と同等であることが求められます。
なお、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する外国人について、既に住居を確保しており、その住居に引き続き住む場合は、この支援を実施する必要はありません。ただし、その住居から退去せざるを得なくなった場合等には、新たな住居の確保に係る支援が必要です。
住居の確保に係る支援については、居室の広さや衛生面等、適切な住居を確保できるよう支援を行う必要があります。居室の広さは、1人当たり7.5㎡以上を満たす必要があります。ルームシェアをする場合は、居室全体の面積を居住人数で割った場合の面積が7.5㎡以上でなければなりません。ただし、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等で、受入れ企業が在留資格変更許可申請(又は在留資格認定証明書交付申請)の時点で既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合は、1人当たり4.5㎡以上を満たせば足ります。
ちなみに住居の確保に関する任意的支援としては、特定技能外国人との雇用契約の解除・終了後でも、次の受入れ先が決まるまでの間に住居の確保が必要な場合は、上記支援を行うことが望まれます。
次に、1号特定技能外国人に対する生活に必要な契約に係る支援内容は次のとおりです。
- 銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設の手続きの補助
- 携帯電話の利用に関する契約の手続きの補助
- 電気・水道・ガス等のライフラインに関する手続きの補助
すでに口座開設等を行っている場合等、明らかに不要である場合は、支援対象外です。
ちなみに生活に必要な契約に関する任意的支援としては、契約の途中で契約内容の変更や解約を行う場合に、手続きが円滑に行われるように必要な書類の提供や窓口の案内を行い、必要に応じで当該外国人に同行する等が望まれます。
(4)生活オリエンテーションの実施
1号特定技能外国人が日本に入国した後(在留資格変更後)、当該外国人が日本における職業生活、日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、入国後(在留資格変更後)、速やかに生活オリエンテーションを行う必要があります。生活オリエンテーションでは、次の内容を網羅する必要がありますが、実施方法は対面でもZOOM等のオンラインでも可能です。
- 日本での生活一般に関する事項(金融機関や医療機関、交通機関の利用方法、交通ルール、生活ルール・マナー等、生活必需品等の購入方法等、災害情報の入手方法、日本で違法となる行為の例)
- 国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続きに関する事項及び必要に応じて同行手続きを補助すること(所属機関等に関する届出、住居地に関する届出、社会保障及び税に関する手続き等)
- 相談・苦情の連絡先、申し出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先(支援担当者の氏名・電話番号等、地方出入国在留管理局、労働基準監督署、ハローワーク、法務局、警察署、最寄りの市区町村役場、弁護士会、大使館・領事館等)
- 外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項(外国人患者の受け入れ体制が整備されている病院の名称、所在地及び連絡先、医療通訳雇入費用等をカバーする民間医療保険)
- 防災・防犯に関する事項、急病その他の緊急時における対応に必要な事項(自然災害・事件・事故等への備え、火災の予防、緊急時の連絡先・場所、警察・消防・海上保安庁等への通報・連絡の方法、気象情報の把握方法、災害時の避難場所)
- 出入国又は労働に関する法令規定の違反を知ったときの対応方法その他当該外国人の法的保護に必要な事項(入管法令に関する知識、入管法令に関する違反場ある場合の相談先及び連絡方法、労働に関する法令違反がある場合の相談先及び連絡方法、雇用契約に反することがあった場合の相談先及び連絡方法、人権侵害があった場合の相談先及び連絡方法、年金の受給権に関する知識及び脱退一時金制度に関する知識とその相談先や連絡方法)
なお、入管HP内にある外国人生活支援ポータルサイトや生活・就労ガイドブックに掲載されている情報が、生活オリエンテーションで提供する情報の参考となりますので、ぜひこちらもご覧ください。
(5)日本語学習の機会の提供
1号特定技能外国人に対して、次のうち当該外国人の希望する方法で、日本語を学習する機会を提供する必要があります。たとえ当該外国人に相当程度の日本語能力があっても、継続した日本語学習の機会を提供する必要があるとされています。そして、この支援を行うにあたり発生する費用は受入れ企業の負担ですが、学習費用は基本的に当該外国人の負担となりますので、過度な負担にならないように留意しなければなりません。日本語学習教材の一例として、文部科学省が提供している日本語学習サイトがありますので、ぜひご参照ください。
- 日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて同行して入学の手続きの補助を行う
- 自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続きの補助を行う
- 当該外国人と合意の下、日本語教師と契約して日本語の講習の機会を提供する
ちなみにこの項目の任意的支援としては、受入れ企業の職員による当該外国人への日本語指導・講習の積極的な企画・運営、日本語能力試験の受験支援や資格取得者への優遇措置、受入れ企業が学習費用の全部又は一部を負担する等です。
(6)相談又は苦情への対応
1号特定技能外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申し出を受けた時は、遅滞なく適切に応じるとともに相談等の内容に応じて当該外国人への必要な助言、指導を行う必要があります。加えて、受入れ企業等は、必要に応じ、相談内容に対応する適切な機関を案内し、当該外国人に同行して必要な手続きの補助を行わなければなりません。なお、相談又は苦情への対応は、1号特定技能外国人の離職が決まった後も、雇用契約が有効である間は行う必要があります。
相談及び苦情への対応は、当該外国人が十分に理解できる言語により実施する必要があります。通訳の確保が難しい場合は、一時的に同僚の外国人就労者を通訳にしたり、翻訳アプリ等を使用したりすることもできますが、プライバシー保護の観点から、詳細な聞き取りについては、通訳を確保した上で適切に対応する必要があります。また、当該外国人が相談等をしたことで、職場での待遇等において不当な取り扱いがなされないようにする必要もあります。
相談・苦情の対応は、特定技能外国人の勤務形態に合わせて、1週間当たり勤務日に3日以上、休日に1日以上対応し、相談しやすい就業時間外(例:午後7時~8時)等に対応できることが求められます。相談・苦情はいつ寄せられるか分からないことから、専用のメールアドレスを設ける等、可能な限り休日や夜間においても対応可能多態性を整えていること、また事故の発生等緊急時の連絡先を設け、基本的にいつでも連絡が受けられる体制を構築することが望まれます。
相談・苦情の対応を行った場合、相談記録書に記録し、14日以内に入管に提出する必要があります。また、支援の実施に関する管理簿として受入れ企業の事業所(登録支援機関に委託している場合は登録支援機関)に雇用契約終了の日から1年以上備えておく必要があります。
ちなみにこの項目の任意的支援としては、相談窓口の情報を一覧にする等して、あらかじめ1号特定技能外国人に情報を分かりやすい形で提供しておくことが望まれます。さらに、当該外国人が仕事中や通勤中に亡くなった場合、その家族等に対して労災保険制度の周知や必要な手続きの補助を行うことも望まれます。
(7)日本人との交流促進に係る支援
1号特定技能外国人と日本人との交流促進に係る支援は、必要に応じ、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や地域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加の手続きの補助を行うほか、必要に応じて同行して各行事の注意事項や実施方法を説明する等の補助を行わなければなりません。
また、日本の文化を理解するために必要な情報として、就労又は生活する地域の行事に関する案内を行うほか、必要に応じて同行し現地で説明する等の補助を行わなければなりません。地域住民との交流を促進させるため、季節の行事等をとらえるなどし、年間を通じて行うことが望まれます。
ちなみにこの項目の任意的支援としては、1号特定技能外国人が各行事に参加できるよう、有給休暇の付与や勤務時間について配慮することが望まれます。また、当該外国人が地域社会で孤立することが無いよう、受入れ企業等が率先して日本人との交流の場を設けていくよう努めることが望まれます。
(8)非自発的離職時の転職支援
受入れ企業が人員整理や倒産等により、1号特定技能外国人との雇用契約を解除する場合は、当該外国人が他の日本の企業との雇用契約に基づいて特定技能1号としての活動が行えるように、次の支援を行う必要があります。1~4のいずれかの支援を行う必要があるのに加えて、5と6の支援はどちらも行う必要があります。7については、登録支援機関に委託していない場合(自社支援の場合)に必要な支援となります。
- 所属する業界団体や関連企業等を通じて次の受入れ先に関する情報を入手し提供する
- ハローワーク等を案内し、必要に応じて当該外国人に同行して次の受入れ先を探す補助を行う
- 当該外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談・職業紹介が受けられるよう又は円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成する
- 職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介を行うことができる場合は、就職先の紹介あっせんを行う
- 当該外国人が求職活動をするために必要な有給休暇を付与する
- 離職時に必要な行政手続について情報を提供する
- 倒産等により、転職のための支援が適切に実施できなくなることが見込まれる時は、それに備えて当該企業に代わって支援を行う者を確保する
契約機関満了前に、特定技能外国人との雇用契約を終了する場合は、受入れ困難に係る届出書(複数人の場合はこちら)と受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書を14日以内に入管に提出する必要があります。さらに、非自発的離職者に対する転職支援を行った場合は、転職支援実施報告書に記載し、14日以内に入管に提出する必要があります。
なお、非自発的離職者を発生させると、受入れ企業としての要件を満たさなくなるため、その時点で雇用している他の特定技能外国人の雇用を継続できなくなるだけでなく、そこから5年間は新たな特定技能外国人を雇用できなくなります。
(9)定期的な面談の実施、行政機関への通報
受入れ企業等の支援責任者又は支援担当者は、1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、当該外国人及びその監督する立場にある者それぞれと定期的な面談(3か月に1回以上)を実施する必要があります。この場では、生活オリエンテーションで提供した日本での生活一般に関する事項、防災及び防犯に関する事項、急病その他の緊急時における対応に必要な事項等を必要に応じて改めて提供することも求められます。そして、この面談は当該外国人が十分に理解できる言語で、対面(場合によっては、対面とオンラインのハイブリッド)で行われる必要があります。また、支援責任者又は支援担当者は、当該外国人との定期面談の場で、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることを知った時は、労働基準監督署その他の関係行政機関へ通報しなければなりません。加えて、資格外活動又は旅券及び在留カードの取り上げ等、その他の問題の発生を知った時は、その旨を地方の入管へ通報しなければなりません。
定期面談を実施したら、定期面談報告書(1号特定技能外国人用・監督者用)を作成し、翌年度4月1日~5月31日までに定期届出一式とともに入管に提出する必要があります。また、支援の実施に関する管理簿として受入れ企業の事業所(登録支援機関に委託している場合は登録支援機関)に雇用契約終了の日から1年以上備えておく必要があります。
ちなみにこの項目の任意的支援としては、当該外国人が自ら通報を行いやすくするために、関係行政機関の窓口情報の一覧をあらかじめ提供しておくことが望まれます。
3.まとめ
この記事では、1号特定技能外国人の支援計画の内容について、詳しくご紹介しました。
特定技能外国人を受け入れる際の支援計画の作成は、受入れ企業にとって必須の義務であり、作成内容が不十分だと入管への特定技能ビザの申請が不許可となる可能性があります。また、ここまで見てきたように、9つの支援項目を最初からすべて自社支援で実施するのは、非常に難易度が高いです。よって、最初は登録支援機関に9つの支援項目の実施をすべて委託し、徐々に自社で支援するというのも一つの方法かと思います。それから、将来的には1号特定技能外国人を支援の必要が無い2号特定技能外国人へ移行できるよう、外国人が長く働ける職場環境を整えることも大切です。(1号から2号への移行についての記事はこちらをご覧ください。)
特定技能ビザを取得するには、支援計画以外にも作成すべき書類がたくさんあります。当事務所では、特定技能ビザを取得するための申請書類の作成代行を行っております。 外国人雇用をスムーズに進めたい企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

この記事の監修者
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。
お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
新着情報・お知らせ
かざはな行政書士事務所

住所
〒739-0041 広島県東広島市西条町寺家
受付時間
10:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日(予約対応可)
対応地域
広島県を中心に、岡山県、山口県、島根県、鳥取県および全国オンライン対応可能