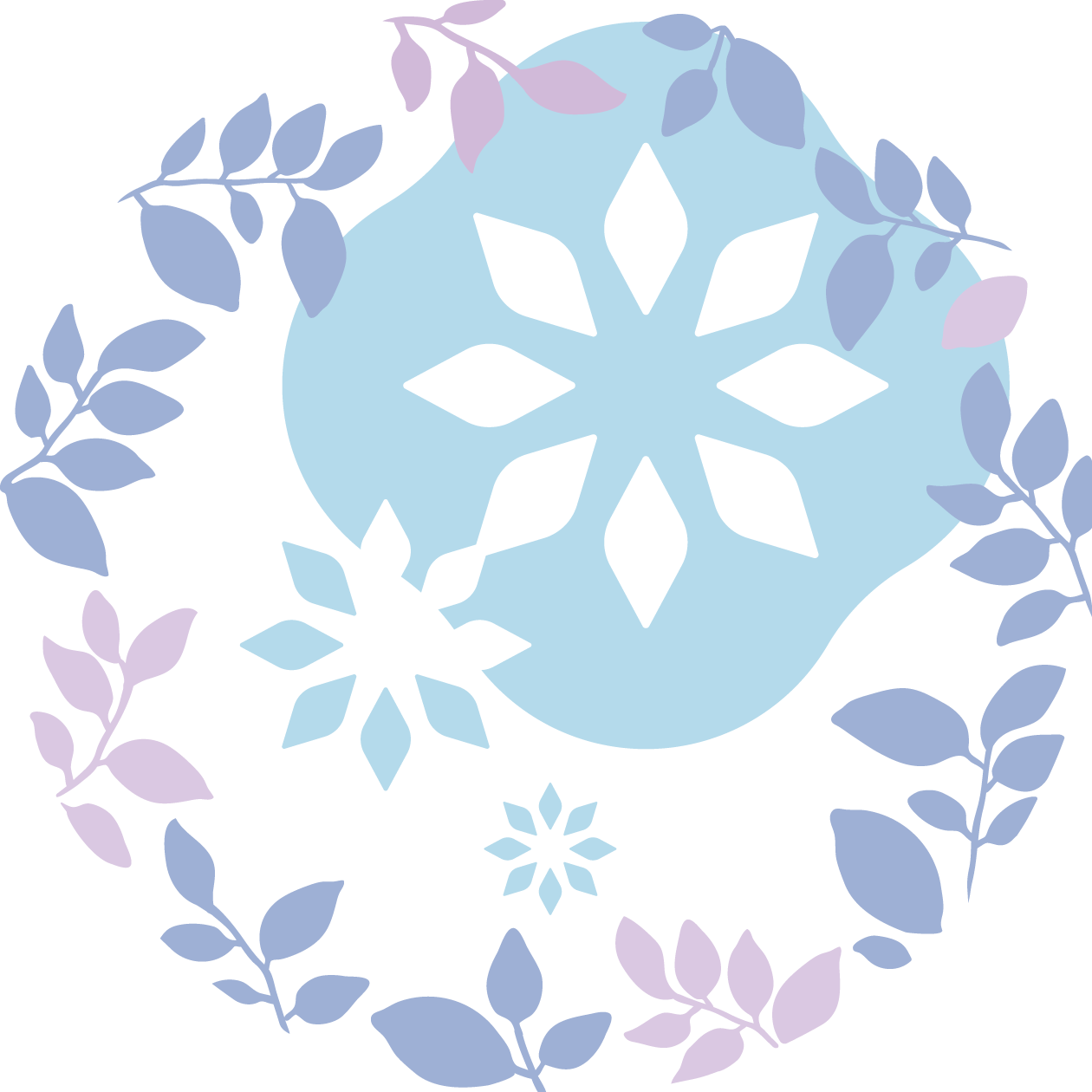特定技能と技能実習の違いについて
更新日:2025年10月2日 投稿日:2025年7月23日

少子高齢化が進む日本では、様々な産業で人手不足が深刻化しています。そこで最近よく耳にするのが、特定技能外国人や技能実習生を雇用して、人材不足を補おうというものです。ですが、この特定技能制度と技能実習制度は、似ているようでその目的や仕組みは異なります。外国人の雇用を検討されている場合、この違いを把握することは非常に重要です。
この記事では、特定技能制度と技能実習制度の違いについて、詳しく解説します。
1.制度の目的
まずこの2つの制度は、目的が全く異なります。
技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を受け入れ、OJT(職場での実務を通じて知識やスキルを習得させる教育訓練)を通じて、技能を移転することを目的として、1993年4月から始まりました。開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力するために創設された制度と言えます。
一方、特定技能制度は、深刻化する人手不足への対応として、人材確保が難しい産業の特定分野に限り、一定の専門性や技能を持ち、即戦力となる外国人を受け入れ、人材不足を解消することを目的として、2019年4月から始まりました。他の就労ビザや技能実習生に認められていなかった単純作業の業務にも従事することができるのが大きな特徴です。
従来の技能実習制度の最終目標は、技能実習終了後に帰国し、技能実習生が習得した技能を活かして母国の発展に貢献することでした。しかし、特定技能制度ができてからは、技能実習2号を良好な成績で修了し、特定技能1号への移行を希望する外国人は、帰国することなく、在留資格変更申請をすることができるようになりました。とは言え、技能実習時の職種や作業を活かして、そのまま特定技能に移行できる関連分野であれば、技能試験や日本語能力試験は免除されますが、関連分野でない場合は、技能試験に合格しなければならないため、注意が必要です。
2.受け入れ可能な産業分野・職種
技能実習制度と特定技能制度はそれぞれ目的が異なるため、外国人を受け入れることができる産業分野や職種も異なります。
まず技能実習制度で受け入れ可能な職種・作業は、91職種・168作業です(2025年7月時点)。厳密に言うと、この職種等は、2号(2年間)・3号(2年間)に移行できる対象職種を指しており、技能実習1号(1年間)のみで受け入れをする場合は、職種制限はありません(ただし、技能習得につながらない単純作業は認められていません)。詳しくはこちらをご覧ください。技能移転を目的とする制度であるため、本国での修得が難しい技能に係る産業分野が選ばれています。
一方、特定技能制度で受け入れ可能な産業分野は16分野(特定技能2号は11分野)です(2025年7月時点)。詳しくはこちらをご覧ください。人材不足解消を目的とする制度であるため、生産性向上や人材確保の取り組みを行っても、人材不足が解消されない産業分野が選ばれています。
このように、2つの制度は目的が異なるため、受け入れ可能な産業分野や職種が若干異なります。技能実習2号から特定技能への移行を希望する場合は、試験が免除される関連分野であるか、確認する必要があります。例えば、技能実習の「漁業関係」、「建設関係」、「繊維・衣服関係」は全ての職種・作業が、関連する特定技能分野へ移行可能となっており、技能実習2号を良好に修了していれば、技能試験も日本語能力試験も免除されます。
一方、「農業・林業関係」、「食品製造関係」、「機械・金属関係」と「その他」に含まれている職種・作業については、関連する特定技能分野にそのまま移行できるものもあれば、そうでないものもあるため、個別に確認する必要があります。関連分野ではない場合は、日本語能力試験は免除されても、技能試験は免除されません。
また、特定技能にある「自動車運送業」は、技能実習制度の職種・作業には含まれていないため、どの職種で技能実習2号を修了してもよいですが、日本語能力試験は免除されても(※)、免許取得や技能試験は免除されません。(※トラック分野のみ。バス・タクシー分野は、N3以上の日本語能力が求められるため、日本語能力試験も免除されません。)
なお、2027年に施行予定の育成就労制度(技能実習制度から移行予定の制度)では、受け入れ可能な産業分野が、特定技能産業分野と同じ産業分野になることが予定されており、現状より外国人材の育成、労働力の確保がスムーズになることが見込まれます。
3.在留期間と受け入れ可能人数
技能実習生と特定技能外国人は、在留期間や受け入れ可能人数についても異なります。
まず、技能実習生は、1号、2号、3号に分かれており、それぞれ在留期間は1号:1年以内、2号:2年以内、3号:2年以内の最長5年です。技能実習生は、実習を経て技能検定試験等に合格することで、1号から2号、2号から3号へステップアップしていくことができます。また、受け入れ可能人数についても制限があります。なぜなら、無制限に技能実習生を受け入れ可能としてしまうと、日本人社員と技能実習生の業務分担やOJT教育の整備が困難となり、技能習得の効果が減少するおそれがあるためです。よって、常勤職員が30人以下の会社は技能実習生3人まで、といったように会社の規模に応じて、受け入れ可能人数に制限が設けられています。なお、2024年12月末時点の技能実習生数は、45万人を超えており、国籍別では1位:ベトナム、2位:インドネシア、3位:フィリピン、職種別では1位:建設関係 、2位:食品製造関係 、3位:機械・金属関係となっています。
一方、特定技能外国人は、1号と2号に分かれており、それぞれ在留期間は1号:3年を超えない範囲で指定され、通算上限5年、2号:6か月、1年、2年、3年のいずれかで更新は無制限となっています。特定技能外国人についても、実務経験を積み、熟練した技能を身に着けた後、同産業分野の評価試験に合格することで1号から2号へステップアップすることができます。また、受け入れ可能人数については、基本的に制限はありませんが、建設分野と介護分野のみ、その事業所の常勤職員の人数までという制限があります。なお、2024年12月末時点の特定技能外国人数は、28万人を超えており、国籍別では1位:ベトナム、2位:インドネシア、3位:フィリピン、分野別では1位:飲食料品製造業、2位:工業製品製造業、3位:介護となっています。
4.2つの制度の比較表
ここまで、2つの制度について、大きな違いを紹介してきました。ここまでの比較に加えて、その他の違いについても表にまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
| 技能実習 | 特定技能 | |
|---|---|---|
| 制度目的 | 国際貢献のため、開発途上国等の外国人を受け入れ、OJT(職場での実務を通じて知識やスキルを習得させる教育訓練)を通じて、技能を移転すること | 深刻化する人手不足への対応として、人材確保が難しい産業の特定分野に限り、一定の専門性や技能を持ち、即戦力となる外国人を受け入れ、人材不足を解消すること |
| 在留資格(ビザ) | 技能実習 | 特定技能 |
| 在留期間 | 1号:1年以内、2号:2年以内、3号:2年以内 | 1号:3年を超えない範囲(通算5年上限)、2号:6か月、1年、2年、3年のいずれか(更新無制限) |
| 外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |
| 入国時の試験 | なし (介護職種のみ入国時、日本語能力試験N4合格レベルであること) | 該当分野の特定技能評価試験と日本語能力試験等に合格すること (技能実習2号を良好に修了した者は免除) |
| 送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |
| 監理団体 | あり | なし |
| 支援機関 | なし | あり (受け入れた会社から個人又は団体が委託を受けた場合は、特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁長官による登録制) |
| 外国人と受け入れる会社とのマッチング | 通常、監理団体と送出機関を通して行われる | 受け入れる会社が直接海外で採用活動を行うことも、国内外のあっせん機関等を通じて採用することも可能 |
| 受け入れ可能な人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | なし(介護分野、建設分野を除く) |
| 活動内容 | 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号) (非専門的・技術的分野) | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 (専門的・技術的分野) |
| 転籍・転職 | 原則不可。ただし、受け入れた会社の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |
| 待遇 | 最低賃金以上かつ日本人労働者と同等以上の報酬額 | 同程度の技能を有する日本人労働者(概ね3年以上の経験者)と同等以上の報酬額 |
| 家族の帯同 | 不可 | 1号:原則不可、2号:配偶者と子どもは可能 |
| 今後の予定 | 2027年に育成就労制度へ移行予定 | 今後も継続予定 |
参考:外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組( 出入国在留管理庁)
5.まとめ
ここまで特定技能と技能実習の違いを解説してきましたが、どちらの制度で受け入れるべきか迷ってしまうことも多々あると思います。
実際に受け入れる際には、まず自分の会社で従事してもらう予定の業務内容が、特定技能か技能実習の対象分野であるかどうかを確認することが大切です。
そしてもし、両方の制度で受け入れることが可能である場合は、以下の視点で検討されてみてはいかがでしょうか?
- 育成の負担が少ない即戦力を求めている⇒特定技能
- 3~5年間の安定的な労働力の確保を求めている⇒技能実習

この記事の監修者
かざはな行政書士事務所
代表行政書士
佐々本 紗織(ささもと さおり)
プロフィール
前職の市役所勤務の中で、国際業務に従事し、外国人支援の仕事に深く関わってきました。
その経験を活かし、行政書士としてより専門的なサポートを行うため、一念発起して資格を取得しました。
2025年5月に、広島県東広島市で入管業務専門の「かざはな行政書士事務所」を開業。
ビザ申請や帰化申請を中心に、外国人の方と企業の皆様を支援しています。
お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
新着情報・お知らせ
かざはな行政書士事務所

住所
〒739-0041 広島県東広島市西条町寺家
受付時間
10:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日(予約対応可)
対応地域
広島県を中心に、岡山県、山口県、島根県、鳥取県および全国オンライン対応可能